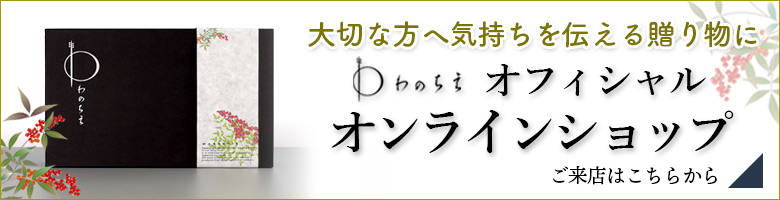近江茶ブランドには何がある?~土山茶と政所茶を知ろう~

土山茶とは
土山茶は、滋賀県甲賀市土山町周辺で栽培されている日本茶です。
滋賀県最大の栽培面積と生産量を誇ります。
1356年に、常明寺の僧純翁が京都の大徳寺からお茶の種子を持ち帰り栽培したことが始まり、と言われています。
土山は滋賀県最大の生産量を誇る近江随一の茶所です。
野州川沿いのなだらかな丘陵地に茶畑が広がっていて、長い日照時間と恵まれた水のおかげで土山茶は育まれました。
その茶葉は長く分厚い葉肉で、味や香りが非常に濃く、二煎目のお茶までも美味しくいただけます。
その味わいはまったりとして奥深く、非常に美味しいです。
土山茶の中でも盛んなのが、茶葉の摘み取りの前に覆いを被せて旨味を増して渋みを抑えるという、かぶせ茶が有名です。

かぶせ茶とは
かぶせ茶とは、茶葉の摘み取り前の段階で覆いを被せて旨味を増し、渋みを抑えて育てられた日本茶の一種です。
かぶせ玉露や熱湯玉露などとも言われています。
かぶせ茶とは煎茶に分類されるお茶になり、製造方法は煎茶や玉露と同じく発酵させず、蒸して熱処理を行います。
かぶせる期間は、芽を摘み取る1週間程度で茶の木そのものに覆いを被せてしまいます。
直射日光を遮って栽培するため、渋みの元であるカテキンが通常の煎茶よりも少なく、逆に旨味の元であるテアニンが多くなります。
覆うことで玉露のように香りも高くなります。
味は煎茶の爽やかさと玉露の旨味を合わせ持ち、熱めのお湯で抽出時間を短くすると爽やかに、ぬるま湯でゆっくりと抽出すると旨味深い味わいになります。

政所茶とは
政所茶とは、近江茶のブランドの中のひとつで、滋賀県東近江市政所町周辺において栽培されている日本茶です。
政所町は滋賀県東部の鈴鹿山脈中に位置しています。
その歴史は古く、室町時代に永源寺五世菅長の越渓秀格禅師が、政所町の水質・地質が茶の栽培に適していると村人に栽培を推奨したことから始まった、と言います。
この地域は寒暖の差がはっきりしており、手摘みで収穫されていることから香りが良く、苦味の中にもほのかな甘みが感じられるのが特徴の、非常に美味しいお茶と言えるでしょう。
茶摘唄でも「宇治は茶所、茶は政所」と唄われているほど、宇治茶と並ぶ茶どころとして全国に知られています。
現在では30軒ほどの農家で生産される、希少な茶になっています。