「発酵」の知恵
古くから私たちは漬物や納豆、味噌、日本酒など発酵食品を日々の食卓に取り入れて生活してきました。発酵食品は、免疫を保ち病気に負けない身体をつくるのにかかせない食材の一つです。発酵とはなにか、発酵が体にもたらす効果についてお話します。

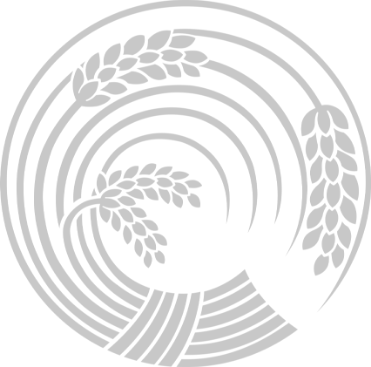
滋賀県は日本のお茶の発祥地とされ、西暦805年頃、伝教大師最澄が唐より持ち帰った茶の種子を比叡山麓の日吉大社あたりに播かれたのが始まりといわれています。
現在は、甲賀市を中心に「近江の茶」として煎茶、かぶせ茶を主流に生産され、農林水産大臣賞を何度も受賞し、「近江の茶」は、高級茶として名声を高めています。
渋み、苦み、旨みなどの独特な味わいをもつ緑茶には、健康によい影響を与えるとされる成分が多く含まれており、実に多様な効果・効能があります。そのなかでも代表的な成分を紹介します。

このように、お茶には他には類を見ない様々な成分が含まれ、人体に取り入れられると複合的な働きをする特徴があります。
しかしこれらの効能は即効的ではないものが大部分なので、活用するためには日常的にお茶を飲む習慣を身につけることが大切です。

上級煎茶をやや熱めの湯で淹れると、カフェインが多く出るので頭脳の働きが活発になり、リフレッシュできます。
カフェインには筋肉刺激効果もあるので、力仕事やスポーツを始める20~30分前に飲み、身体を動かしている最中でも20分~30分おきに 1杯飲むといいと言われています。 スポーツ後は、汗をかいて水分不足の状態になっているので、番茶やほうじ茶など軽いお茶を多めに飲んで下さい。
口の中をさっぱりさせるほうじ茶やウーロン茶が合います。
中級煎茶、番茶、ほうじ茶はどのような食事にも合い、たっぷりと飲むことが出来ます。
食中毒予防や虫歯予防のためには、カテキンが多い中級煎茶をやや熱めのお湯で淹れるといいです。
特に胃の弱い人は、空腹時に玉露や抹茶のような濃厚な茶を飲むと、胃の粘膜などを刺激することがあるので、番茶、ほうじ茶、玄米茶などがいいです。
カフェインの含有量が多い上級煎茶が良いです。高めの湯で淹れると、カフェインが多くなり、苦渋みが強くなりますが、より効果は期待できます。
妊婦や乳児は体内にカフェインがとどまる時間が長くなるため、取り過ぎに注意が必要です。お茶の葉の量を標準的な量(1人分3g)の半分か三割くらいにして淹れるか、玄米茶や低カフェイン茶にするのが良いです。
カフェインが多い玉露や上級煎茶を飲むと人によっては眠れなくなるので、お茶の葉の量を半分に減らして淹れるか、玄米茶や低カフェイン茶にするのが良いです。カフェインは摂取後1~2時間で血中濃度が最高濃度になり、半分が体外に排出されるまでに血中で3時間、体組織全体では5~6時間かかります。摂取したカフェインの大半(95%)が体内から消失するのは16~20時間後といわれています。
お茶は、ちょっとした淹れ方の違いで、驚くほど味わいが変わるものです。好みに応じて、自由に楽しむことで一層味わい深いものになります。
旨味成分であるアミノ酸類は、お湯の温度に関係なく溶出しますが、渋味・苦味成分であるタンニン・カフェインは、お湯の温度が高くなるほど溶出しやすいので、低めの温度のお湯で淹れましょう。






茶葉は、産地により1年に2~4回摘採されます。
温暖な鹿児島では4月上旬、静岡では4月中旬、京都などでは4月下旬から5月上旬に新茶摘みが始まることが多いようです。
少しでも摘採の時期がずれてしまうと、茶葉の品質が落ちてしまうため、生産農家は足しげく茶畑にかよい、摘採の時期を慎重に見極めます。
一番茶摘採後、50日前後に行う。北部や高地など気温の低い地域では二番茶までで収穫を終わらせる地方が多い。
二番茶摘採後、35~40日前後に行う。地域によっては、三番茶を摘み採らずに、秋口に摘む「秋冬番茶」もあります。
日本では一般に機械による摘採方法がとられていますが、機械による摘採が困難な急傾斜にある茶園や、玉露やてん茶園、一番茶初期の極めて上級な煎茶の摘採は、手摘みで行われています。海外の主な産地では、手摘みが主流です。手摘みでは、一芯二葉または一芯三葉(上部の2~3葉)を摘み取ります。
お茶は、茶葉の摘採時期によって味や香りが異なります。
このうち一番茶には、旨み成分であるテアニンなどアミノ酸類、カフェインが最も多く含まれ、二番茶、三番茶の順に減少していきます。 そのため新茶は、渋味と苦味が少ない一方、旨味が多く若葉のようなさわやかな香りが特徴です。
また、初夏の強い日差しをたっぷり浴びた二番茶は、他の茶葉に比べカテキンの含有量が多いのですが、爽やかな渋みが味わえます。
一方、三番茶は、どうしても風味が落ちてしまうため、市場に出回る量は少ないです。 ところが、最近では三番茶以降の秋口に摘採されるお茶(秋冬番茶)に血糖値をおさえる効果があると言われ、その価値が見直されています。 摘採する年によっても、旨みや渋みが異なり、好みの銘柄を続けて飲んでみるのも一つの楽しみになるかもしれません。
もちろん、二番茶、三番茶も味や香りは劣るとはいえ、身体に優しい成分が凝縮されていますので、シーンに応じて選んでみるのもおすすめです。

日本茶の保存について幾つかの注意点をお話します。
日本茶は、紅茶などに比べて変質しやすいため、保存方法には十分な注意が必要です。
日本茶を変質させる主な原因は4つ(①酸素、②湿気、③温度、④光(紫外線))ですが、中でも酸素は、緑茶にとって一番の大敵です。酸素によって、カテキンが酸化してお茶の色を悪くしますし、ビタミンCは酸化によって分解してしまいます。
また、光(紫外線)も葉緑素を変化させて緑色のお茶を変色させますので、お茶の保存には、酸素に触れない、光を通さない容器を選択します。また、酸化を助長するのが、湿気(水分)と温度ですので、密封して湿気を吸わせないこと、高温を避けて、できるだけ温度が低い場所で保存することが大切になります。
この4つの原因からお茶を遠ざければ、変質を防ぐことができますが、ご家庭では、できるだけ半月~1ヶ月位で飲み切る量を購入することをお勧めします。また、最近の茶は、空気や湿気、光も通さない素材で作られた袋で売られています。
さらに、真空にしたり、袋の中の空気を抜いて窒素ガスに置き換えて酸化を防いでいるものもあります。こうしたパッケージのものは、そのまま冷蔵庫に保存できますが、いくつか注意が必要です。
一つめは、お茶はニオイを吸着しやすい性質がありますから、冷蔵庫の他の食品から出る様々なニオイを吸着しないように、さらにチャック付きのビニール袋などに入れて、口をしっかり閉じること。二つめは、冷蔵庫のドアの開閉などによる温度変化の少ない場所に保存すること。三つめは、冷蔵庫から出して、冷たいまま開封しないことです。
冷蔵庫から出すと、外気との温度差によって容器の表面が結露しますが、冷たいまま開封すると、お茶の表面も結露して、お茶を湿気させる悪い条件を作ってしまいます。開封する前に、夏なら半日、冬でも2~3時間おいて、袋の中の温度が、周りの気温と同じになってから開封して下さい。